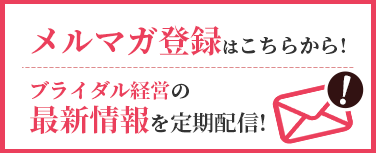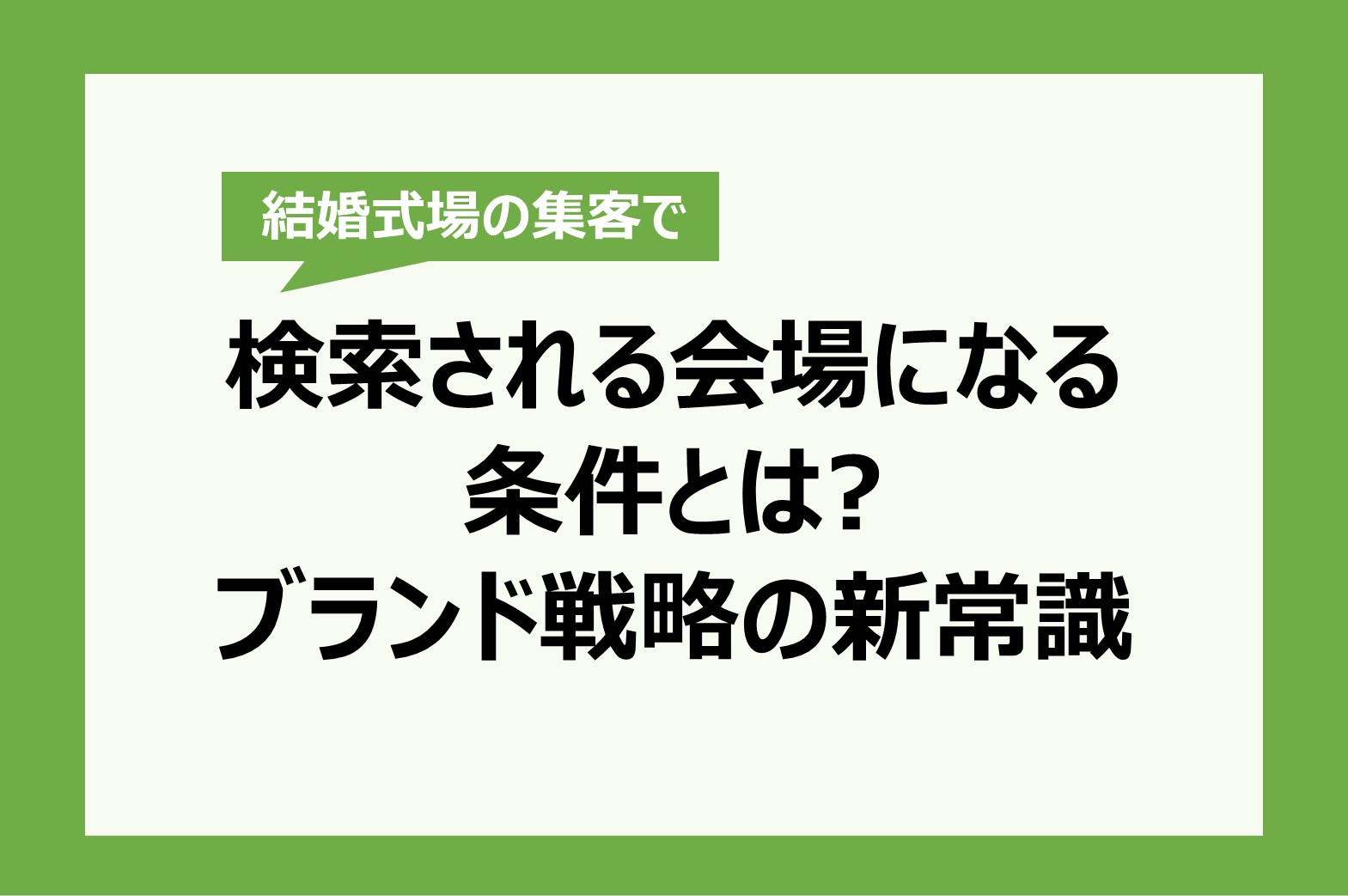
ポストコロナ、デジタルシフト、そして価値観の多様化──。
結婚式の価値が「イベント」から「人生の節目の体験」へと再定義されるなか、集客構造にも変革が求められています。
特に、媒体依存型の集客モデルに限界が見えはじめている今、「指名検索で選ばれるブランド」になることが、ブライダル経営の成否を左右する重要な戦略要素となりつつあります。
“調べられる式場”になる時代──SNS・AI時代の検索行動にどう備えるか
これまでのブライダル業界では、情報誌やポータルサイトといった媒体への依存度が高い集客モデルが主流でした。もちろん、これらの媒体が果たす役割は今も大きいですが、顧客が情報を得るチャネルが多様化した現代においては、それだけに頼ることはリスクとなり得ます。また近年、お客様の情報収集行動は劇的に変化しています。
SNSでの口コミやInstagramでの写真検索、そしてYouTubeでの動画視聴を経て、自分たちに合う商品やサービスを「自力で探す」という行動が一般化しています。
さらに近年では、GoogleのAI検索やChatGPTなどの生成AIを使って、「○○市のナチュラル系で料理が評判の式場」といった個別かつ文脈的な検索が日常化しています。
その結果、「結婚式場」で検索されるよりも、「(ブランド名) 口コミ」「(ブランド名)ウェディングフェア」など、ブランド名を伴った“指名検索”が行われるかどうかが、集客成果に大きな差を生むようになっています。
これは、顧客が比較検討に入る前から「候補に入っている」状態であり、広告に頼るのではなく「記憶に残る」ブランドとして存在していることの証拠です。
実際に、地域一番店と呼ばれる会場の多くは、この「指名検索」経由の流入が全体の中で非常に高い比率を占めています。
媒体頼みではなく、「検索される会場」として想起される設計こそが、これからのブライダル集客の要となるのです。
「選ばれる存在」になるためのマーケティング戦略
では、どのようにすればお客様から「指名される存在」になれるのでしょうか?
その鍵は、自社のブランド価値を確立し、お客様の心に「第一想起」を生み出すことにあります。そのためには、単に広告を打つだけでなく、多角的な視点からマーケティング戦略を構築する必要があります。
具体的な手法で例えば、マーケティングの4Pモデルの再構築があります。
4P:マーケティング実行プランの再設計
Product(商品)
商品=式場、だけではありません。新郎新婦にとっての体験価値をどう設計するかが本質です。「家族との時間」「自己表現の場」など、新郎新婦が得たい価値や結婚式を行う意味に焦点を当て、商品コンセプトを再定義する必要があります。
Price(価格)
競争力のある価格とは、「安い」ことではなく価値に見合った納得感があること。見積もりの設計や説明フローの中に、顧客理解と感情納得を織り込む工夫が欠かせません。
Place(流通チャネル)
ポータルサイト任せから、自社集客のためSNS・Googleビジネスプロフィール・口コミ・YouTubeなど、ブランドの“直接検索”を生むチャネルを構築することが重要です。
Promotion(販促)
広告ではなく、記憶に残る情報設計が必要です。TVCMやリール動画など、想起を促すコンテンツを戦略的に配置し、「あの式場、聞いたことある」「見たことある」と思わせる認知の蓄積がカギです。
ブランド名で探される存在になるために
今の市場では、「選ばれる会場」ではなく「探される会場」になることが、生き残りと成長の条件です。
そのためには、感覚的な集客から、設計されたマーケティング戦略への転換が必要です。
誰に、何を、どのように届けるのか?
なぜ、他ではなく“自社が”選ばれるのか?
それを中長期でどう再現・拡張していくのか?
私たち船井総研主催で10年後も生き残るためのブランド戦略、マーケティング再構築をテーマに、経営研究会(勉強会)を開催しています。ご興味があれば「ブライダル経営研究会」で検索いただければ詳細が分かります。