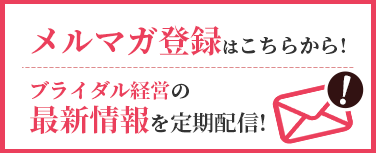前回のコラムに引き続きブライダル経営研究会6月例会のダイジェストをお届けしたいと思います。
第二講座では、日本の韓国フォトウェディングシーンにおいて、現場の第一線で活躍されている方をゲスト講師にお招きし、人材育成からビジネスモデルの変革に至るまで、多岐にわたる具体的なご経験と、その中で培われた「実践的な経営視点」について深く掘り下げてまいりました。
今回は、特に「人」と「働く環境」に焦点を当て、具体的な取り組みをご紹介します。
重要なのは人が輝く「職場(環境)」を作るということ
一般的に、組織において「成果を出す」ことに重点が置かれがちですが、まずは働くスタッフ一人ひとりが「楽しく、やりがいを感じられる」環境こそが、結果として最高のパフォーマンスを生み出します。実際に成果を上げられているゲスト企業様が構築したチームでは、3年間で仕事が嫌で辞めるスタッフが一人もいなかったそうです。これは、単に福利厚生が充実しているというだけではなく、日々の業務における細やかな配慮と、明確な役割設定によるものです。
では、具体的にどのような取り組みがとられたのでしょうか。ゲスト企業様では、以下の点を重視されました。
「できない理由」ではなく「どうすればできるか」の思考転換:
何か問題が発生した際、できない理由を探すのではなく、「どうすればできるか」を常に考え、解決策を導き出すことを徹底しました。例えば、お客様の要望に対して「それはできません」と即答するのではなく、「どうすればそのご要望を叶えられるか」を徹底的に考え抜く姿勢を貫きました。たとえそれが会社の既存ルールと異なることであっても、お客様にとっての最善を追求する姿勢は、結果として顧客からの信頼と感謝に繋がっています。
「褒め合う文化」の醸成:
スタッフ同士がお互いの良い点を見つけ、積極的に褒め合うことを奨励しました。人は、自分の良いところを理解されている相手からの指摘であれば、悪い点も素直に受け入れやすいものです。これにより、建設的なフィードバックが機能し、チーム全体の成長を促しました。私たちは、スタッフが互いの良い部分を認め合い、支え合うことで、個々のモチベーションとチームワークが向上すると考えています。
「新しいことへの挑戦」を歓迎する風土:
「昨日と同じことしかやっていない」状態を避けるため、常に変化と成長を求める姿勢を大切にしました。新しいアイデアや提案に対しては、たとえそれが現状では実現が難しくても、頭ごなしに否定せず、まずは尊重し、実現に向けて皆で検討する文化を築きました。これにより、スタッフは臆することなく、自由に発想し、提案できるようになり、それが結果としてサービス向上や新たな価値創造に繋がります。
人材育成における具体的な体制と権限委譲
ゲスト企業様は、フォトグラファー2名体制をとっておりました。メインのフォトグラファーの技術レベルに左右されることなく、常に一定以上のクオリティを保つためであり、それだけでなくアシスタントの育成にも大きく貢献しています。アシスタントは、単に機材を運ぶだけでなく、ライティングの調整や撮影の補助、お客様とのコミュニケーションサポートなど、高度なサポートスキルを習得することで、メインのフォトグラファーへの道筋が明確になります。このような体制は、チーム全体の技術力向上と安定したクオリティ維持に不可欠であると私たちは考えています。特に、内製化を進めることで、アシスタントのスキルアップがチーム全体の資産となり、外部委託では得られない高いチームワークとサービスの質を実現できます。
人材育成と同時に、重要視するべきは「権限委譲」です。特に採用面接においては、一般的に経営層や人事が行うことが多いなか、事業責任者が面接の場に立ち応募者に対して、単なる雇用関係ではなく、「共にビジョンを達成する仲間」という対等な関係性を提示し、相互理解を深めることを重要です。
これにより、入社後のミスマッチを防ぎ、早期離職率を大幅に低減させることができます。表面的なスキルや経験だけでなく、その人物の人間性や価値観が、チームの文化とどれだけフィットするかを見極めなければなりません。
本講演では、もはや一過性のブームと言えない、いちジャンルとして確立された韓国フォトウェディングについて、本場韓国と日本の新郎新婦のニーズの違いについても明らかになりました。
韓国フォトウェディングに対するリアルなニーズ
韓国では、流行の移り変わりが早く、人気のトレンドに集中する傾向があります。新郎新婦、特に花嫁の意見が強く反映され、皆と同じスタイルで撮影し、共有することに価値を見出す文化があります。結婚式を挙げないカップルでも、写真は必ず撮るという習慣があり、撮影された写真は寝室に飾られ、夫婦喧嘩の際には初心を思い起こすための「お守り」となるというエピソードは、写真が持つ深い意味合いを物語っています。
それに対して日本では、流行を取り入れつつも、どこかで「自分たちらしさ」や「人とは違う」個性を求める傾向があります。また、結婚式の組数は減少しているものの、結婚式の代わりに写真だけを撮る「前撮り・後撮り」のニーズは増加しており、複数回撮影するカップルも増えています。さらに、韓国だけでなく、中国や台湾のフォトグラフィーも、その独特のスタイルで注目を集め始めており、今後の市場拡大の可能性を秘めています。
このことから、日本のフォトウェディングスタジオは、単に韓国のスタイルを模倣するだけでなく、日本の花嫁のニーズに合わせてローカライズし、オリジナリティを追求していくことが求められます。そして、ポータルサイトの数字だけでは測れない、SNSなどを通じた個別のフォトグラファーやスタジオへの直接依頼といった新しいニーズを捉えることが、今後の成長の鍵となるでしょう。フォトウェディングのニーズは減少しているという声も聞かれますが、それは「顕在化されたニーズ」の数字に過ぎないかもしれません。実際には、フォトウェディングという選択肢そのものが多様化し、写真のニーズ自体が様々な形で拡大していると私たちは見ています。
「変わらないことは退化すること」。コロナが収束して以降、急激に市場が成熟しつつあるフォトウェディング業界にも同様のことが言えます。
本講座で語られたように、変化を恐れず、人材育成と働く環境への投資、そしてお客様のニーズを掴み寄り添うことで、新たな価値創造と事業成長は十分に可能です。
第三講座では、約30年のキャリアを持つ写真館・フォトスタジオ専門のコンサルタントが登壇し、「時流適応」と「原理原則経営」をテーマに、変化の激しい時代を乗り越えるための普遍的な経営術と、現代の市場に合わせた具体的な戦略について深掘りしていく予定です。
次回コラムもご期待くださいませ。
ブライダル経営研究会のお試し参加(経営者のみ・初回のみ)無料でご参加いただけます。>